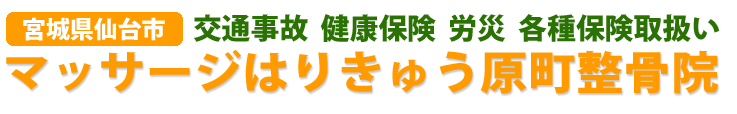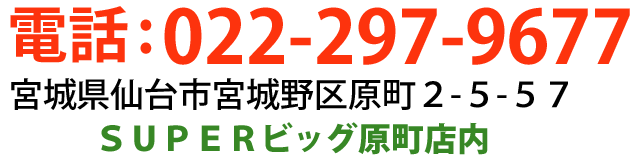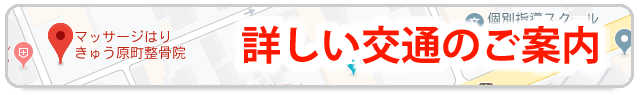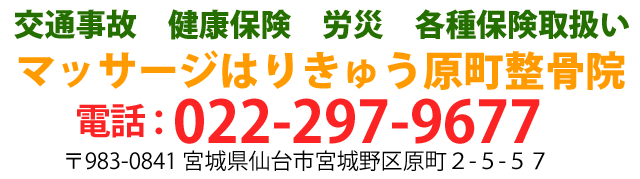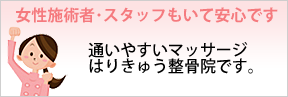




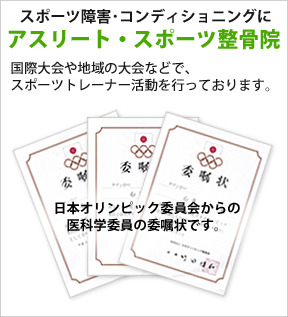

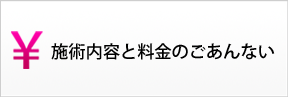
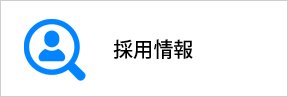
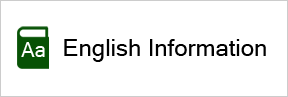
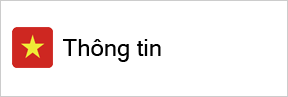
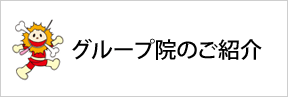

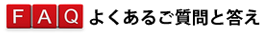
A.はじめて来院される場合は健康保険証をお持ちください。
健康保険証の他、交通事故、各種保険、労災、生活保護等の取り扱いもしています。
Q.駐車場はありますか?
A.ございます。
SUPERビッグ原町店駐車場をご利用下さい。
Q.女性スタッフはいますか?
A.女性スタッフもおります。
女性もお気軽にご来院頂いております。
猫背になると負担がかかりやすい部位はどこでしょう?
頸椎と腰椎
解説:猫背では頭部が前方に移動するため、約5〜6kgある頭の重さを支える頸椎に大きな負担がかかります。また骨盤が後傾し、腰椎の生理的前弯が失われることで腰にもストレスが集中します。
骨盤がゆがむと起こりやすい症状はどれ?
腰痛や下肢のしびれ
解説:骨盤は脊柱と下肢のバランスを保つ基盤。ゆがみが生じると腰椎椎間関節や仙腸関節に負荷が集中し、坐骨神経痛などの症状を誘発します。
長時間のデスクワークで痛みやすい筋肉はどこ?
僧帽筋・大胸筋・腸腰筋
解説:座位で前かがみになると胸筋は短縮、僧帽筋上部や肩甲挙筋は過緊張、腸腰筋は短縮して腰椎を引き込み、肩こり・腰痛の原因になります。
スマホ首(ストレートネック)の原因は何?
頸椎の前弯消失
解説:頭部を前傾した状態を長時間続けることで頸椎の自然な前弯(30〜40度)が失われます。その結果、椎間板や頸椎後方筋群に大きなストレスが加わり、頭痛や肩こりを招きます。
O脚を放置すると将来的にリスクが高まるのは?
変形性膝関節症
解説:O脚では内側関節裂隙が狭くなり、膝の内側半月板や軟骨が摩耗。長期的に進行すると関節変形や歩行障害を引き起こします。
血流を良くするために最も効果的なのは?
下肢の筋肉を動かす
解説:特に下腿三頭筋は「第2の心臓」と呼ばれ、収縮により静脈血を心臓に送り返します。ウォーキングやストレッチが効果的です。
冷え性の改善に役立つ食べ物はどれ?
生姜・にんにく・唐辛子
解説:これらは血管拡張作用や代謝促進作用があり、末梢血流を改善します。東洋医学的にも「温性食品」とされます。
足のむくみを改善するセルフケアで正しいものは?
足首の曲げ伸ばし運動
解説:下腿の筋ポンプ作用を高め、リンパ還流を促します。マッサージや入浴も併用するとさらに効果的です。
冷房で冷えやすい部位はどこ?
腰から下
解説:下半身は心臓から遠く、静脈還流が滞りやすいため特に冷えやすいです。末梢循環障害を防ぐため、靴下や腹巻での保温も有効です。
入浴で血流を改善するのにおすすめの方法は?
40℃前後のお湯に10〜15分浸かる
解説:ぬるめのお湯は副交感神経を優位にし、末梢血管を拡張させます。高温浴は交感神経を刺激し、逆に血流改善効果が落ちることもあります。
睡眠不足が続くと一番最初に現れやすい不調は?
自律神経の乱れ
解説:睡眠不足は交感神経優位を招き、動悸・頭痛・消化器不調など全身に影響を与えます。
健康な成人の1日の理想的な歩数は?
約8,000〜10,000歩
解説:生活習慣病予防のためには8,000歩、そのうち速歩を20分含めることが推奨されています(厚生労働省ガイドライン)。
水分不足になると起こりやすいのは?
血液粘度の上昇
解説:脱水により血液が濃縮されると血栓リスクが上昇。頭痛や集中力低下、便秘の原因にもなります。
正しい椅子の座り方で重要なのはどれ?
骨盤を立てて坐骨で座る
解説:坐骨を支点に骨盤を立てることで脊柱のS字カーブが保たれ、腰椎への負担が軽減されます。
朝起きて最初に飲むと良い飲み物は?
常温の水
解説:寝ている間に失われた水分を補い、腸蠕動を促進します。冷たい水は胃腸を刺激しすぎることがあるため常温が理想です。
鍼灸でよく使う「ツボ」の意味は?
経絡上の反応点
解説:ツボ(経穴)は気血が集まる場所。刺激することで全身の調整や局所の血流改善を促します。
「足三里」というツボは何に効果があると言われる?
胃腸機能の改善・免疫力向上
解説:膝下3寸に位置し、古来より「長寿のツボ」と呼ばれます。消化機能を高めるほか、疲労回復にも有効とされます。
東洋医学で「気」「血」「水」が乱れるとどうなる?
体調不良や病気の原因になる
解説:気は生命エネルギー、血は栄養、水は体液を指し、この3つの失調は頭痛、冷え、むくみ、倦怠感など多様な症状を生じさせます。
ツボ押しを行うのに最も適したタイミングは?
入浴後や就寝前
解説:筋肉が温まり血流が良いときに行うことで、より深部まで刺激が伝わりやすくリラックス効果も高まります。
腰痛予防に効果的な運動は?
体幹筋トレーニング(プランクなど)
解説:腹横筋や多裂筋などの深層筋を鍛えることで腰椎を安定させ、腰痛の再発を予防します。
肩こり改善におすすめのストレッチは?
僧帽筋・肩甲挙筋のストレッチ
解説:デスクワークで短縮・緊張しやすい筋群を伸ばすことで筋血流が改善し、こりの軽減につながります。
筋肉は運動後、どのタイミングで伸ばすと効果的?
運動後すぐ(クールダウン時)
解説:筋温が高い状態でストレッチすることで柔軟性が向上し、筋肉痛や損傷予防にも有効です。
急に運動するとケガをしやすい理由は?
筋温が低く、柔軟性が不足するから
解説:ウォームアップなしでは筋・腱の伸張性が低く、肉離れや靱帯損傷のリスクが高まります。
正しいウォーキング姿勢で意識すべき点は?
背筋を伸ばし、踵から着地する
解説:重心移動をスムーズに行うことで下肢関節の負担を減らし、効率よくエネルギー消費できます。
骨を丈夫にする栄養素はどれ?
カルシウム+ビタミンD
解説:カルシウムは骨の主要成分、ビタミンDは腸管での吸収を助けます。日光浴も重要です。
疲労回復に良い栄養素はどれ?
ビタミンB群
解説:糖質・脂質・タンパク質の代謝に必須で、エネルギー産生を助け疲労感を軽減します。
ビタミンCが多い食べ物は?
赤ピーマン・キウイ・柑橘類
解説:抗酸化作用やコラーゲン合成に関与し、免疫機能を高めます。熱に弱いため生食が望ましいです。
腸内環境を整えるために効果的な食品は?
食物繊維・発酵食品
解説:食物繊維は善玉菌のエサとなり、発酵食品は善玉菌そのものを供給します。両方を組み合わせることが理想的です。
日本人に不足しがちな栄養素はどれ?
鉄・カルシウム・ビタミンD
解説:食生活の変化で摂取量が低下しています。
腸内フローラとは何のこと?
腸内細菌叢の多様性を花畑に例えたもの
解説:腸内には約1,000種類・100兆個の細菌が共生し、そのバランスが健康に直結します。近年は「腸内細菌叢解析」が医療研究でも注目されています。
善玉菌の代表とされる大腸菌の種類は?
大腸菌(非病原性株)・ビフィズス菌
解説:大腸菌は全てが悪いわけではなく、腸内環境を安定させる無害株も存在します。ビフィズス菌や乳酸菌は代表的な善玉菌です。
発酵食品が腸に良い理由は?
プロバイオティクス作用
解説:発酵食品に含まれる生きた微生物や代謝産物が腸内細菌叢に働きかけ、腸管免疫を強化します。
腸内環境を整えると期待できる効果は?
便通改善・免疫機能向上・精神安定
解説:腸内細菌が産生する短鎖脂肪酸は腸粘膜保護・免疫調整作用を持ち、さらに腸脳相関を通じてメンタルにも影響します。
交感神経と副交感神経をまとめて何という?
自律神経系
解説:意識とは無関係に内臓や血管を調整。交感神経は「戦う・逃げる」、副交感神経は「休む・修復」の働きを担います。
自律神経が乱れると起こりやすい症状は?
めまい・不眠・動悸・消化器不良
解説:交感・副交感神経の切り替え不全により恒常性が崩れ、全身に多彩な症状が出ます。
手や足がしびれるのは、どの神経が関わっている?
末梢神経
解説:脊髄神経から分岐した末梢神経が圧迫されると、感覚異常や運動障害が出現。坐骨神経痛などが代表例です。
反射神経の反応が早いのはなぜ?
脊髄反射経路を介するから
解説:感覚入力が大脳を経由せず脊髄で直接運動ニューロンに伝達されるため、即座に反応できます。
ストレスで優位になりやすいのは交感神経?副交感神経?
交感神経
解説:ストレス負荷下では交感神経が優位となり、心拍数増加・血圧上昇・筋緊張が生じます。慢性的に続くと不眠や高血圧につながります。
腸腰筋はどの筋肉から構成され、主な作用は何でしょう?
大腰筋と腸骨筋(+小腰筋)からなり、股関節屈曲を担う
解説:腸腰筋は体幹と下肢をつなぐ唯一の筋群で、大腿を持ち上げたり、体幹を前屈させたりする作用があります。歩行・走行・階段動作に不可欠です。
腸腰筋が弱くなると起こりやすい症状は?
腰痛・股関節痛・転倒リスク増大
解説:腸腰筋の筋力低下は骨盤・腰椎の不安定性を招き、腰痛の原因に。さらに下肢の振り出しが弱くなり、つまずきや転倒につながります。
腸腰筋が過緊張すると起こりやすい姿勢は?
反り腰(腰椎過前弯)
解説:短縮した腸腰筋が腰椎を強く前方に引き込み、腰部椎間関節や椎間板へのストレスを増やします。
腸腰筋と腰椎椎間板ヘルニアにはどんな関係がある?
腸腰筋の緊張が症状を悪化させる
解説:腸腰筋が硬いと腰椎前弯が強調され、椎間板への圧迫が増加。坐骨神経痛の増悪因子になります。
腸腰筋が加齢で衰えると特に問題となるのは?
歩行速度の低下と転倒リスク
解説:大腿を引き上げる動作が困難になり歩幅が小さくなります。ロコモティブシンドロームの重要因子です。